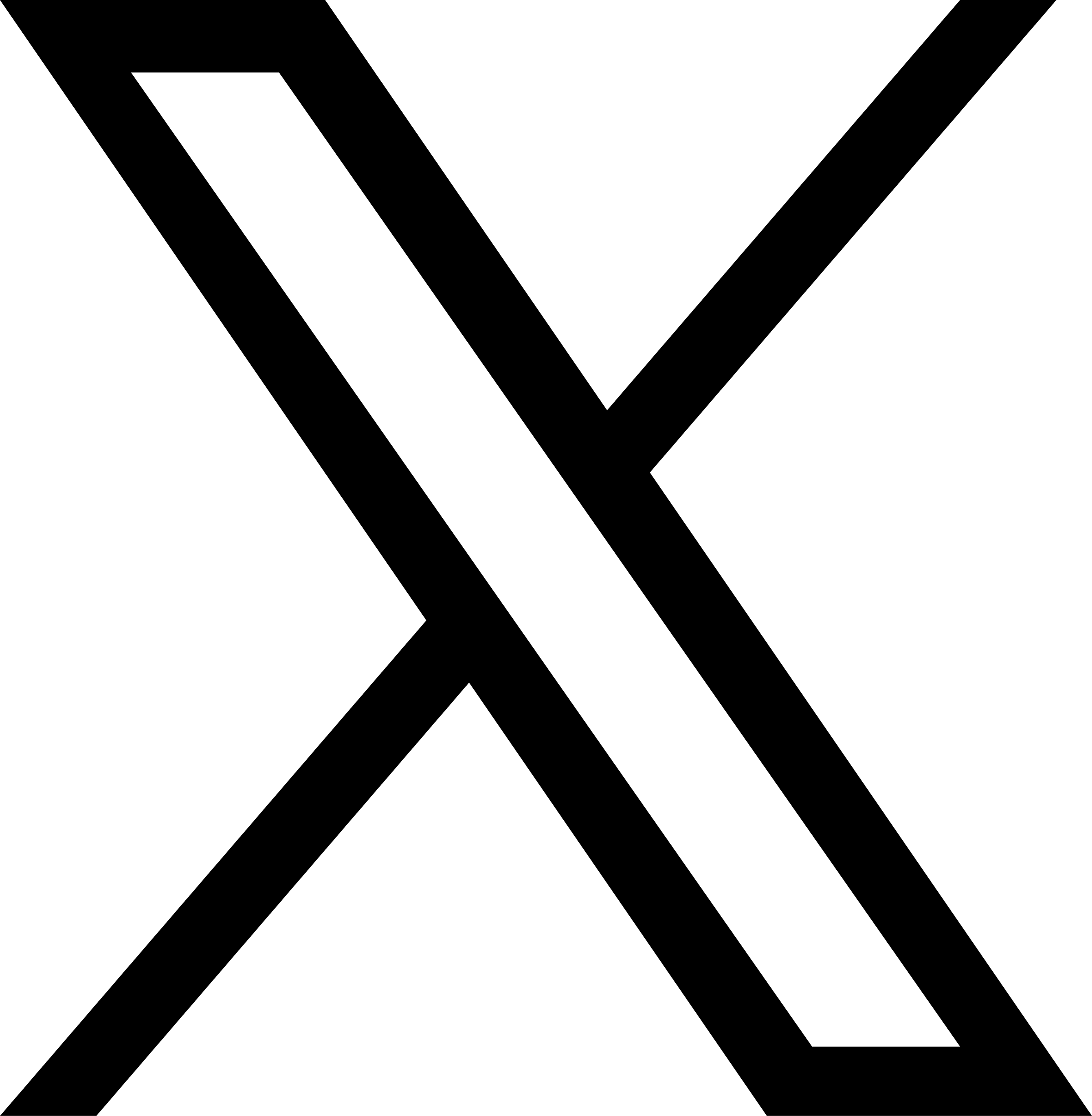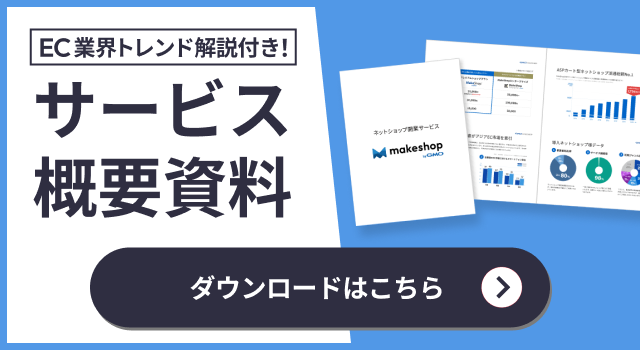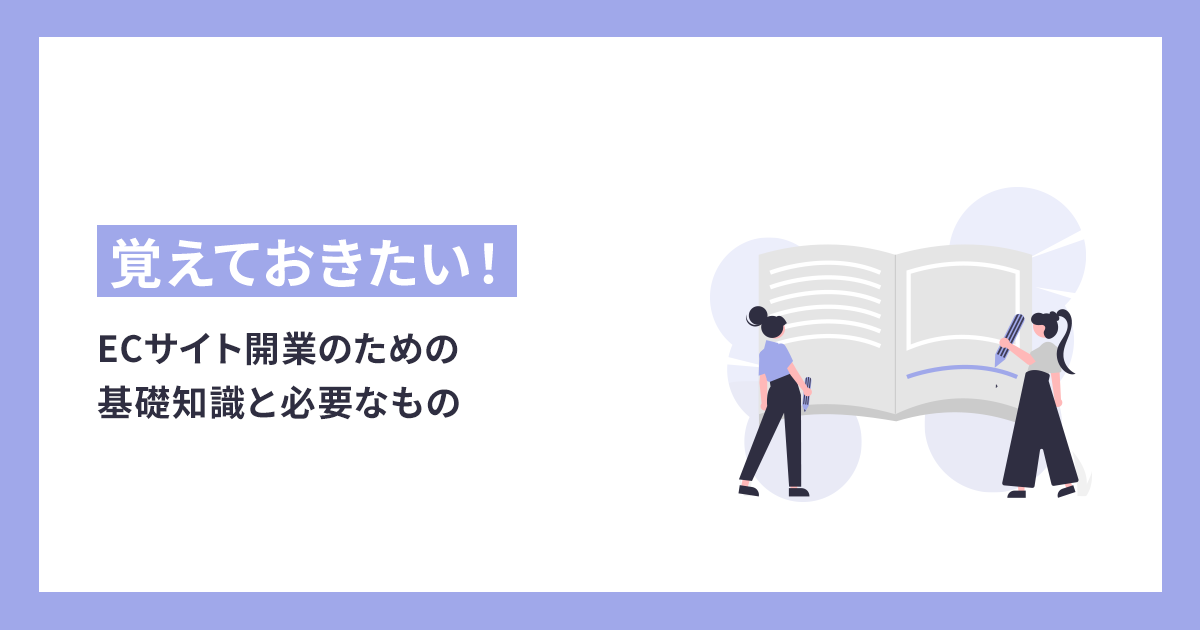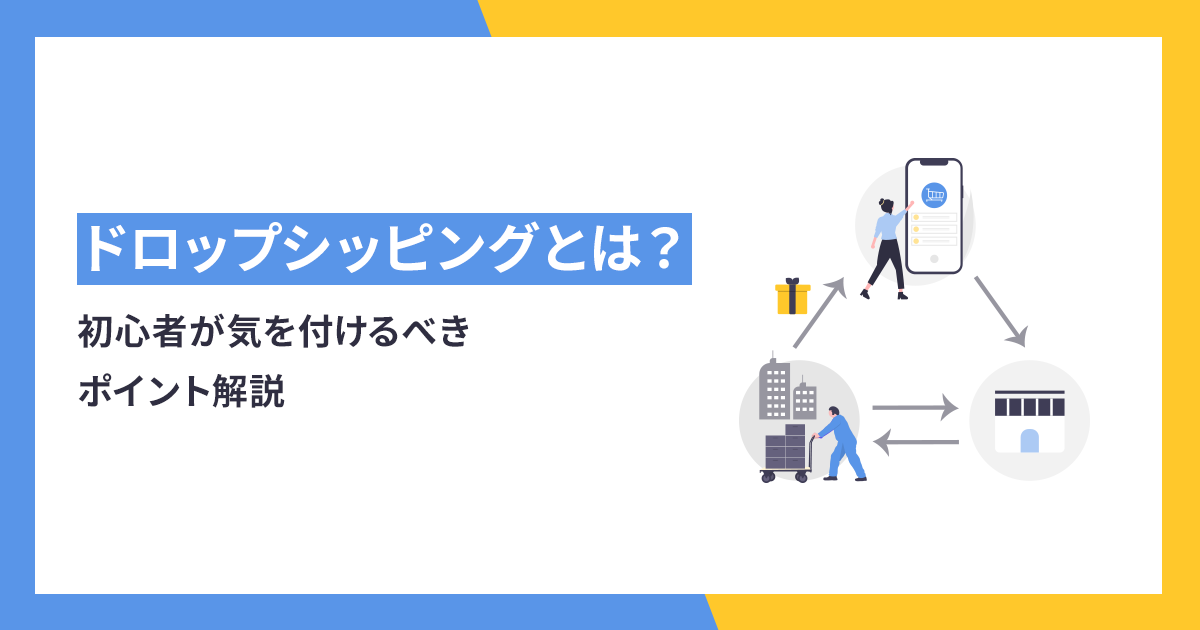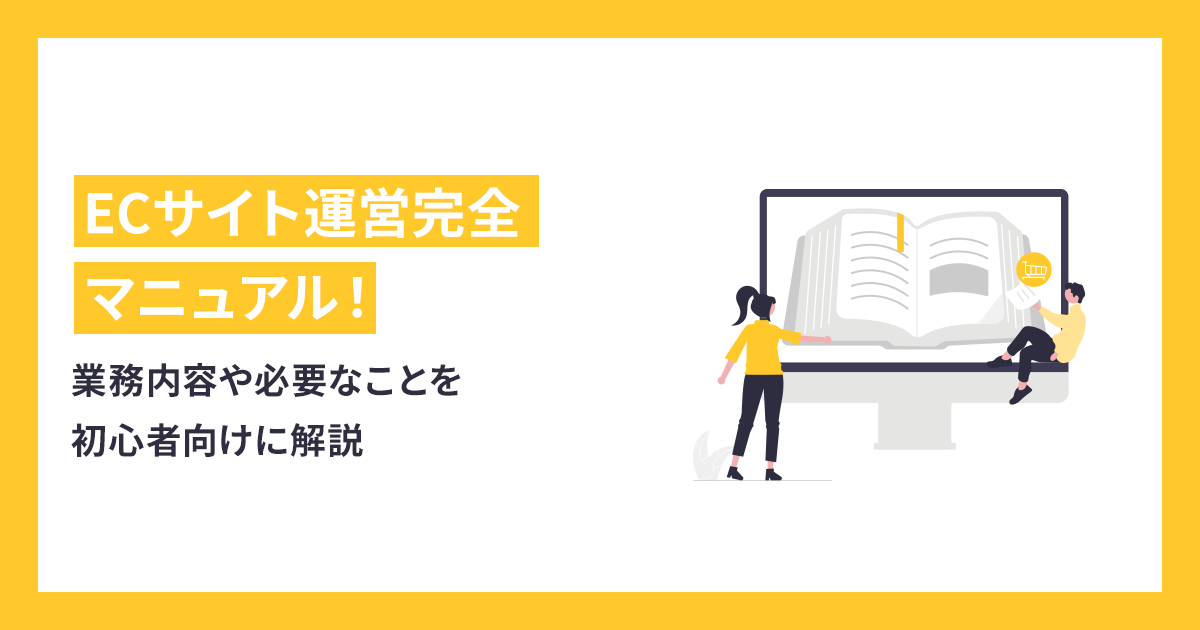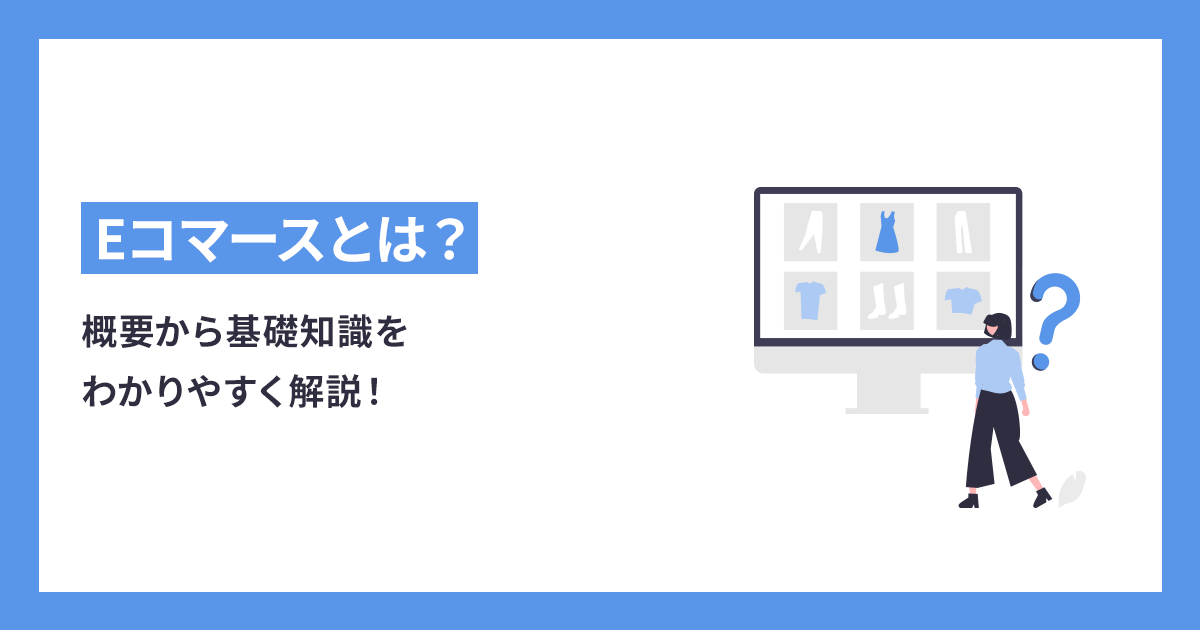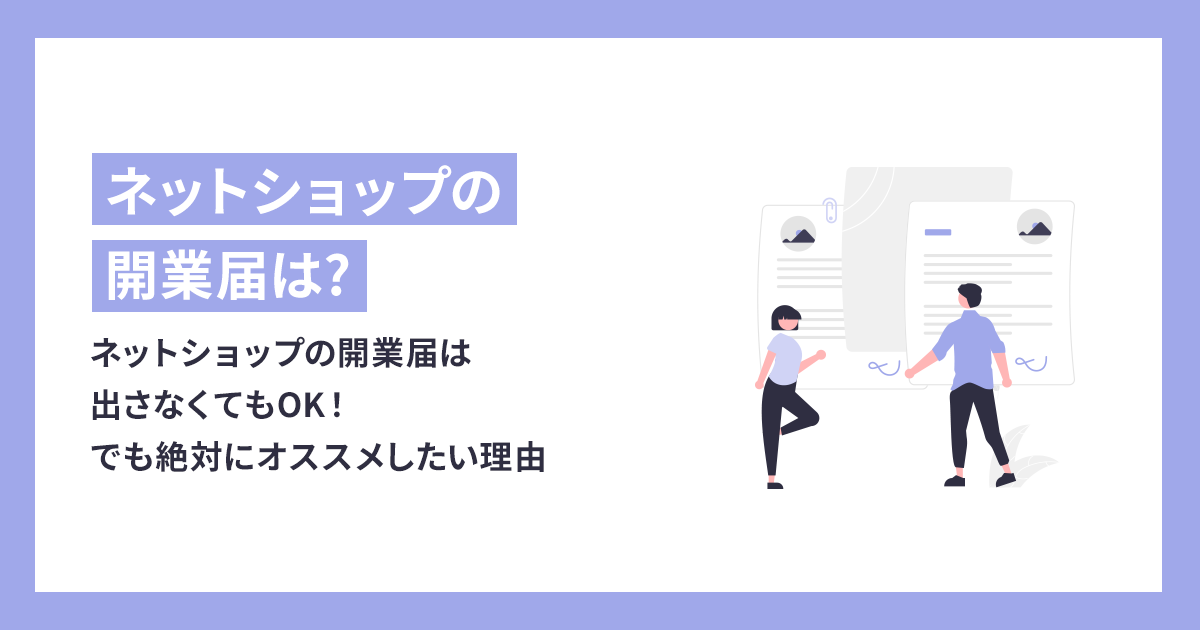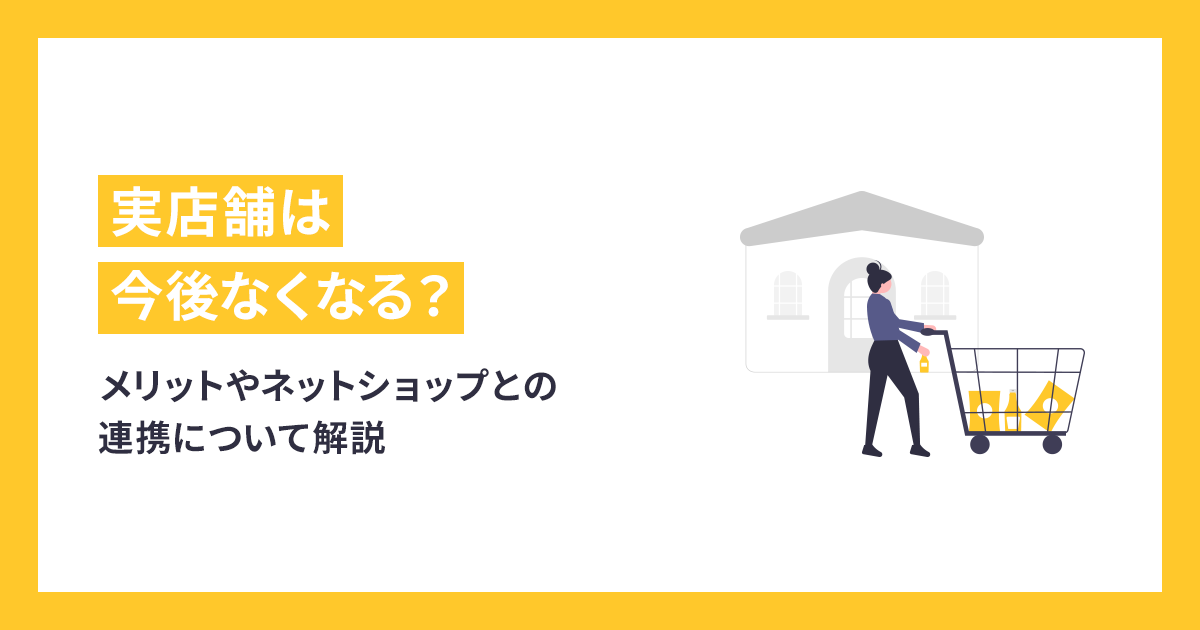【2024年】食品ECの市場規模とEC化率の推移を見る!課題感や成功のポイント
食品分野のECは一般的な食品EC、ネットスーパー、サブスク型ECの3種があり、現在発展中の分野です。この記事では食品ECのメリット・デメリット、成功のためのポイントを詳しく解説します。
食品ECとは?大きく3種類の販売方法がある

食品ECには大きく分けて下記3つの販売方法があります。
- 一般的な食品EC
- ネットスーパー
- 定期販売(サブスクリプション型)EC
以下、詳しく解説します。
販売方法1.一般的な食品EC
「一般的な食品EC」とは、下記のような食品を販売するECサイトです。
- 生鮮食品
- 野菜
- 飲料
- 酒類
- 加工品
一般的な食品ECは、スーパーなどの小売店が上記の食品を自社ECサイトで販売したり、Amazonや楽天市場といったECモールで販売したり、形態はさまざまです。
近年では農業や漁業を営む生産者が、小売店を介さずに自社ECサイトでエンドユーザーに直接販売するケースも多く、一般的な食品ECは多様化しています。
販売方法2.ネットスーパー
「ネットスーパー」は、オンライン上で注文を受注し、実店舗であるスーパーマーケットから個人宅に配送する販売形態です。全国に展開している大手スーパーマーケットなどがネットスーパーを導入しており、家に食品が直接届く手軽さから利用者が増えています。
2020年以降猛威をふるったコロナ禍の影響で「実店舗が存在しないネットスーパー」などもでてきており、生活様式の変化に合わせて、スーパーマーケットの概念が変わりつつあるといえるでしょう。
販売方法3.定期販売(サブスクリプション型)EC
近年、定期的に食品を配達してくれる「定期販売(サブスクリプション型)EC」も注目されています。新鮮な野菜やお肉などはもちろん、温めるだけでおいしく食べられる惣菜を定期販売する食品ECもあります。
食品は毎日食べるものだからこそ、定期販売と相性がよいです。定期販売は毎月安定した収益が見込めるビジネスモデルでもあるため、多くの企業が参入しています。
食品ECの市場規模は?EC化率の推移を見る
経済産業省が2023年8月に公開した報告書によると、日本のBtoC-EC市場は22.7兆円で「食品、飲料、酒類」は2.7兆円と最大のシェアを占めています。
コロナ禍の影響によりオンラインで食品を購入する人も増えたため、前年比の伸び率は全体で一番高く、約9%増加しました。
一方で「食品、飲料、酒類」のEC化率は4.16%と低い数値。「書籍、映像・音楽ソフト」の52.16%や「生活家電」の42.01%と比べて、食品分野のEC化率はまだまだ発展途上ということがわかります。
食品系ECが抱える課題

近年、食品ECの市場規模は成長していますが、多くの課題を抱えているのも事実です。主に下記3つの課題が挙げられるでしょう。
- 生鮮食品など鮮度が重要な食品と相性が悪い
- 実店舗の利便性に劣る
- 利益を出しにくい
以下、詳しく解説します。
課題1.生鮮食品など鮮度が重要な食品と相性が悪い
ECサイトで生鮮食品を販売する際、実際の商品をユーザーに見せられません。生鮮食品は鮮度によって味が変化するため「実物を手にとって選びたい」というユーザーは、食品ECの利用率が低い傾向にあります。
課題2.実店舗の利便性に劣る
ECサイトで食品を注文した場合、商品が手元に届くまでに時間がかかります。食材の買い忘れなど緊急性の高い場面では、生活圏内にある実店舗のほうが欲しい食材をすぐに購入できるため、利便性が高いといえるでしょう。
課題3.利益を出しにくい
食品ECは”利益率が低い”という課題があります。食品は家電製品などと比べて単価が安い場合がほとんどですが、鮮度を保つために保存方法や配達方法を工夫しなければなりません。単価が安い場合、送料に関しても大きなコストを占める要因となります。
また、食品には賞味期限や消費期限があり、廃棄コストも発生します。ほかの分野のECサイトと比べて多くのコストがかかるため、利益を出しにくいビジネスモデルといえるでしょう。
食品ECを展開するメリット

食品EC運営には課題も多いですが、メリットも存在します。食品ECを展開するメリットは、主に下記5つです。
- 商圏・販路の拡大
- いつでも受注できるため機会損失を防げる
- 商品の魅力を詳細に伝えられる
- ニッチな商品でも取り扱える
- ユーザーの声を収集・反映させやすい
以下、詳しく解説します。
メリット1.商圏・販路の拡大
「商圏や販路を拡大できる」という点は、食品ECを展開するうえで大きなメリットです。食品を取り扱う多くの実店舗は、地元顧客をターゲットにしているため、人口の多い都会であれば競合店が多く、人口の少ない過疎地であれば集客数が限定されるという課題を抱えています。
ただ、食品ECを展開するとターゲットは全国のユーザーに拡大します。広告やSNSなどを活用することで高い集客効果を見込める点は、大きなメリットといえるでしょう。
メリット2.いつでも受注できるため機会損失を防げる
食品ECは365日24時間受注可能なため、ユーザーが欲しいと思ったときに商品を注文できます。閉店時間がある実店舗と比べて、機会損失を防げるのです。
メリット3.商品の魅力を詳細に伝えられる
実店舗では数多くの商品を実際に陳列する必要があるため、商品1つ1つの魅力を詳細に伝えることはむずかしいです。一方で食品ECであれば、商品ページにテキストを記載し、商品の魅力を丁寧に伝えられます。
オススメの調理法などを記載することで、成約率や購入後の顧客満足度を向上させられるでしょう。
メリット4.ニッチな商品でも取り扱える
食品ECは「ニッチな商品でも取り扱える」というメリットがあります。”ニッチ”とは「多くの人には不必要でも確実に需要がある商品」のことです。
実店舗であるスーパーマーケットやコンビニなどは、売れ残りを避けるためにニッチな商品を仕入れにくいです。ニッチな商品を探しているユーザーは近所の実店舗で手に入らないため、オンライン上で目当ての商品を検索して購入します。
定番商品と共にニッチな商品をECサイトで販売すれば、売上を向上させられるでしょう。
メリット5.ユーザーの声を収集・反映させやすい
食品ECでは、注文完了画面や注文確認メールにかんたんなアンケートを掲載できるため、ユーザーの声を収集・反映させやすいというメリットがあります。
アンケート結果をもとにECサイトの改善を実施でき、顧客満足度を向上させられるでしょう。
食品ECを成功させるためのポイント

食品ECを成功させるためには、6つのポイントがあります。
- ECでしかできない独自性を打ち出す
- 実店舗では難しい商品情報量を充実させる
- 利便性の高いサイト構築をする
- 顧客がリピートしやすい販売方法にする
- さまざまな配送方法など物流システムに注力する
- SNSを活用して顧客とのタッチポイントを増やす
以下、詳しく解説します。
ポイント1.ECでしかできない独自性を打ち出す
食品ECを成功させるためには、実店舗との差別化が必須です。なぜなら、まったく同じ商品を販売しているのなら、すぐに買える実店舗のほうが利便性が高いからです。
実店舗との差別化を図るために「ECならではの独自性」を追求しましょう。たとえば「重い商品ばかりを販売するECサイト」や「輸入スパイスを専門に取り扱っているECサイト」など、実店舗にはない魅力を取り入れることで、オンライン上で食品を購入する理由ができるのです。
ポイント2.実店舗では難しい商品情報量を充実させる
実店舗では商品棚のスペースに限りがあるため、1つ1つの商品説明を詳細に記載できません。一方で食品ECでは、1つ1つの商品ページに「商品の魅力」を詳細に記載できます。
商品の基本情報はもちろん、商品のこだわりや生産者の想い、食材を美味しく食べるためのレシピなど、商品の魅力をできるだけ伝えて成約率を向上させましょう。
ポイント3.利便性の高いサイト構築をする
食品ECを成功させるためには「利便性の高いサイト構築」を意識しましょう。ユーザーが快適にショッピングできないと、離脱される可能性が高いからです。
たとえば、デザイン性を重視しすぎて「どこにどんな商品があるかわからない」ECサイトになってしまうと、目当ての商品を見つけられずに離脱されます。
ECサイトの利便性について第三者に感想を求めたり、ユーザーにアンケートを取ったり、常に「お客さま目線」で利便性を追求しましょう。
ポイント4.顧客がリピートしやすい販売方法にする
食品ECを成功させるためには、リピート率を高めることが重要になります。リピート率を向上させることで売上が安定し、既存顧客の口コミなどから新規の集客も可能だからです。
定期販売サービスを提供したり、お役立ち情報をメールマガジンで配信したりして、リピート率を向上させるための施策を実施しましょう。
ポイント5.さまざまな配送方法など物流システムに注力する
食品ECは温度管理が重要な商品も多いため、配送方法や物流システムを最適化させる必要があります。
具体的には、冷凍や冷蔵に対応した発送方法の確立や、温度管理を徹底した在庫保管場所の確立など、商品のクオリティを保つために配送・物流に注力しましょう。
ポイント6.SNSを活用して顧客とのタッチポイントを増やす
食品ECを成功させるために、SNSを最大限活用することも重要になります。SNSはレシピ動画などが人気コンテンツのため、食品ECと相性がよいからです。
またSNSは、生産者のこだわりや商品の魅力なども効果的に発信できます。ユーザーをSNSからECサイトへスムーズに流入できれば、集客数を大幅に向上させられるでしょう。
大手ネットスーパー各社の取り組み

すでに食品を販売する実店舗を運営している事業者は、大手ネットスーパーの事例を参考にするとよいでしょう。
ここでは大手ネットスーパー各社の取り組みを紹介します。
Amazonフレッシュ
「Amazonフレッシュ」は2017年4月にAmazonが開始したサービスで、生鮮食品から日用品まで17万点以上の商品を取り扱うネットスーパーです(関東の一部エリアのみ利用可能)。
Amazonプライム会員は追加登録不要で利用でき、朝8時から深夜0時まで2時間毎にお届け時間帯を指定できるため、さまざまなライフスタイルに合わせて利用できます。
食品を最適な環境で管理するために6つの温度帯の倉庫を完備し、優れた物流システムで最短2時間でお届けしてくれます(関東の一部エリアのみ)。
ユーザーの利便性を第一に考えたネットスーパーとして、参考になるでしょう。
楽天西友ネットスーパー
「楽天西友ネットスーパー」は大手ECモールを運営する楽天(Rakuten)と、全国にスーパーマーケットを展開する西友(SEIYU)が合同で運営しているネットスーパーです。
全国に展開している西友の拠点を活用し、全国17都道府県で利用可能。楽天ポイントが利用できるため、楽天ポイントを消費したいユーザーにも多く利用されています。
2021年7月から専用のスマホアプリを提供しており、ユーザーはスマホからかんたんに注文可能です。全国で利用できるという点や、ユーザーの利便性が高いという点で非常に参考になるネットスーパーといえるでしょう。
オイシックス・ラ・大地
「オイシックス・ラ・大地」は、有機野菜や無農薬野菜を宅配するサービスや、栄養バランスの取れた惣菜を定期販売するサービスを提供しています。
商品のお届け時には、段ボールや説明書に「食材を美味しく食べるための説明書き」が詳細に記載されており、顧客満足度の向上につながっています。
オイシックス・ラ・大地は定期販売に力をいれているため、リピーターの獲得方法など、参考になることも多いでしょう。
「MakeShop」による食品ECの構築事例5選

かんたんにECサイトを構築できる「MakeShop」は、食品ECの事例も豊富です。ここでは「食品ECの構築事例5選」をご紹介します。
事例1.三島食品 公式オンラインストア
「三島食品 公式オンラインストア」は、ふりかけや調味料をメインに販売している食品ECです。ECサイトを見てみると、商品を探しやすく見ていて疲れないデザインが特徴的で、利便性を意識していることがわかります。
一般消費者向けの商品とは別に業務用商品も販売しており、リピート率向上の施策も参考になるでしょう。
事例2.ポップコーンパパ
「ポップコーンパパ」は、32種類のポップコーンを取り扱う食品ECです。ポップコーンの専門店ということで、ニッチな食品を取り扱っている食品ECといえるでしょう。
「おつまみ系」や「あまい系」など、カテゴリー分けも直感的でわかりやすく、ポップコーンへのこだわりなどもしっかりと記載しています。
ニッチな食品を扱いたい事業者は参考になるでしょう。
事例3.本神戸肉森谷商店
「本神戸肉森谷商店」は明治6年創業の老舗精肉店が営む食品ECで、神戸牛をメインに取り扱っています。
年齢層の高いターゲットに合わせて、見やすさを重視したサイトデザインを採用しており、リピート率向上に貢献しています。また「実店舗と同じ感覚でお肉を購入してもらいたい」と、100g単位で高品質なお肉を販売。利便性を高める施策も実施しています。
高級な神戸牛はギフトと相性がよく、ギフト戦略にも力をいれているため、さまざまな面で参考になる食品ECサイトといえるでしょう。
事例4.観音山フルーツガーデン
「観音山フルーツガーデン」は、和歌山県で育ったフルーツや加工品を販売している食品ECです。
ECサイト内では旬のフルーツを使ったレシピや、フルーツの豆知識を発信しており、顧客満足度を高める施策が実施されています。
運営している農場では、みかん狩り運営やフルーツパーラー運営をしているため、ECサイト経由で実店舗の集客にもつなげています。
実店舗と食品ECのどちらも運営したい事業者は、参考になるでしょう。
事例5.減塩専門店 無塩ドットコム
「減塩専門店 無塩ドットコム」は、減塩や無塩食品などに力をいれている食品ECです。ECサイト内では高血圧食や腎臓病食も提供されており、ニッチな食品も取り扱っています。
定期購入にも力をいれており、ステップメールでの販促は参考になるでしょう。
食品ECを開設する際に必要な手順と許可
食品ECは必要な資格や許可があったり、開設の手順がすこし複雑です。ここでは「食品EC開設までの手順」と「食品EC運営に必要な資格と許可」をご紹介します。
食品EC開設までの手順
食品ECを開設する際、通常のECサイトとは異なる手順が必要です。開設までの主な手順は下記のとおりです。
- 営業する施設の図面を用意して保健所に相談する
- 営業許可の申請をする
- 営業施設の検査を受ける
- 営業許可証の交付を受ける
- ECサイトの構築をする
- ECサイトの構築が終わったら営業を開始する
上記の手順はあくまで一例です。各自治体によって手続きの流れが異なるため、必ず管轄の保健所に問い合わせてください。
食品ECサイトの構築をする際、食品販売に強い「MakeShop」がおすすめです。多くの事業者がMakeShopで食品ECを開設しており、公式ホームページで多くの事例も紹介しています。
ぜひ導入事例集をダウンロードして、参考にしてください。
食品EC運営に必要な資格と許可
食品EC運営には「食品衛生責任者」という資格と「食品衛生法に基づく営業許可」という許可が必要です。資格や許可の取得方法は各自治体によって異なるため、管轄の保健所に相談してみてください。
まとめ

コロナ禍をきっかけに食品ECの利用者は増えており、それに伴って多くの企業がオンライン上で食品を販売しています。食品を取り扱っている事業者にとって、今後食品ECの重要度は増していくでしょう。
また、年々食品ECの流通額は増えていますが、他の分野のECに比べて食品ECのEC化率はまだまだ低く、発展途上といえます。競合他社が少ないうちに参入し、先行者利益を獲得しましょう。